SERIES
消えた灯火たち
戦後、若くして散った10人の詩人|全7回連載
一枚の遺影から

群馬県立土屋文明記念文学館の展示室に、一枚の写真があります。セーラー服を着た少女。きちんと結ばれたリボン、真っ直ぐにカメラを見つめる瞳。どこにでもいそうな、普通の女学生の肖像です。
しかし、この少女は卒業からわずか3ヶ月後、自らの手で命を絶ちました。1949年(昭和24年)6月1日。服毒自殺。享年17歳。
彼女の名は、長沢延子。
戦後日本文学史において、彼女の名前が大きく記されることはありません。教科書に載ることもなく、文学賞を受賞したこともありません。しかし、彼女が遺した言葉は、死後20年を経て、1960年代末の全共闘世代によって ”発見” され、東大安田講堂のバリケードの中で読まれることになります。
なぜ、無名の少女が書いた詩が、時代を超えて共鳴したのか。今回は、長沢延子という「戦後精神史の亡霊」を訪ねます。
戦後桐生という場所――閉塞と虚無の風景

長沢延子は1932年(昭和7年)、群馬県桐生市に生まれました。桐生は「織都(しょくと)」と呼ばれる織物の町で、江戸時代から絹織物の産地として栄えてきました。しかし、彼女が幼少期を過ごした1930年代から40年代は、戦争と敗戦という激動の時代でした。
空襲こそ免れたものの、桐生もまた戦後の混乱から無縁ではありませんでした。価値観の転倒、食糧難、そして何より、これから何を信じて生きればいいのか、という精神的な虚無。大人たちは昨日まで「天皇陛下万歳」と叫んでいたのに、今日は民主主義を説いています。そうした欺瞞を、感受性の鋭い子供は敏感に感じ取ります。
延子が育った家庭環境についての詳細は多くは伝わっていませんが、彼女の詩や手記からは、家族との深い軋轢が浮かび上がります。家という場所は、彼女にとって安らぎの場ではなく、自己を抑圧し、窒息させる牢獄でした。
1949年3月15日、延子は女学校を卒業します。しかし、その直後の3月26日、彼女は友人に「死のうと思っている」と告げ、服毒自殺を試みます。この時は未遂に終わりました。
しかし、彼女の死への意志は揺らぐことはありませんでした。身辺整理を行い、自分の書いた詩や手記を清書した5冊のノートを友人たちに託して、6月1日、再び服毒。今度は、帰らぬ人となりました。
戒名は、美徳院温良妙延清大姉。その穏やかな響きは、彼女の内面にあった激しい炎とは、あまりに対照的です。
「幻の十二階」を読む――焼け落ちた塔の幻影

朧な物語のはじまり(1946年8月・14歳)
ここで取り上げるのは、延子が14歳だった1946年(昭和21年)8月に書かれた創作詩「幻の十二階」です。 副題に「おぼろな物語ヨリ」と添えられたこの作品は、まるで悪夢の一場面を切り取ったかのような、幻想的でありながら鋭い痛みを伴う構成になっています。
終戦からわずか一年。敗戦直後の混乱と虚脱が渦巻く時代に、14歳の詩人はどのような問いを世界に突きつけたのでしょうか。 作品の核心には、現代を生きる私たちにも通底する「なぜ、理不尽に命は奪われるのか?」という鋭い命題が据えられています 。
幻の十二階 ――おぼろな物語より――
私はたしか何かの本で読んだのだ
あの倒れた十二階の上に
いちどられた若者の血を
おお紅蓮の炎よ 私には見える
若者が燃える塔の中で
あかくあおく霊を燃やしているのが――呪われた塔よ!
血に燃える十二階よ!
あゝ私には見える
あの若者の血に乾く唇が
ギラつく眼と青白い生命が――血に燃える青い瞳よ
打ち上げる花火の中に
お前は何故死んだのだ
この塔を守るためにか?
「俺たちが悪いんじゃない
呪われた塔よ!
お前が燃えればいいのだ」若者よ 何故呪うのだ
友よ私が死んだからとて : 長沢延子遺稿集(出帆新社)より
全身をふるわす
限りない血の恐怖
青白い生命はもえるもえる
あゝ
倒れてもたおれても宙に浮く
幻の十二階
燃えゆく塔と青年の叫び
「幻の十二階」は、ある塔と一人の青年を巡る劇的な情景を描いた詩です。
夜空に聳える十二階建ての高塔が炎に包まれ、その中で若い男性が今まさに焼け死のうとしています。 その瀬戸際で、語り手(あるいは作中の何者か)は彼にこう問いかけます。
「お前は何故死んだのだ/この塔を守るためにか?」
命が尽きようとする青年に発せられたこの叫び。それに対し、火に吞まれゆく青年は絶叫して答えます。
「俺達が悪いんじゃない/呪われた塔よ!」
自分たちの死は自らの過ちではない。この塔が呪われているからだ――。 ここには、塔を守ろうとして命を落とす無念さと、それでもなお塔を呪うしかない、やり場のない怒りと悲しみが凝縮されています 。
そして衝撃的なのは、青年が炎に焼かれ崩れ落ちた後の光景です。 塔は焼け落ちるのではなく、なお ”宙に浮く幻の十二階” として、そこに残り続けるのです 。
残された幻影――宙に浮く「十二階」の寓意

燃え尽きたはずなのに、幻として浮かび続ける塔。 延子はこの「幻の十二階」に何を幻視したのでしょうか。
舞台となる ”十二階” とは、かつて東京浅草に実在し、関東大震災で崩壊した「凌雲閣(りょううんかく)」を連想させます。延子はこのかつてのシンボルを、敗戦後の日本に幻として蘇らせました 。
多くの研究や解釈において、この幻の塔は敗戦によって崩壊したはずの、旧来の国家観やイデオロギーの象徴だとされています 。
- 若者(青年): 戦争で命を奪われた兵士たち
- 塔(十二階): 「国体」=かつての日本、あるいは戦争という虚構
青年の「呪われた塔よ!」という叫びは、「誰のせいで自分たちは死なねばならなかったのか」という、戦争で青春を奪われた世代の悲痛な断罪です 。 どれだけ尊い命が犠牲になっても、虚構の塔は何事もなかったかのように亡霊のように漂い、人々を惑わせ続ける。 この皮肉な結末には、戦争の虚無と、無情な現実への痛烈な批判が込められています 。
虚無で終わらせないために――延子の問いの原点
当時、延子が暮らしていた群馬県桐生の街にも、復員兵や進駐軍があふれ、人々は奇妙な解放感と絶望を抱えていました。 しかし、彼女の詩には少女らしい甘い抒情も、戦後の安易な解放感もありません。そこにあるのは、虚偽に満ちた世界への悲哀と、静かで冷徹なニヒリズムです 。
この詩を読み終えた後、私たちの心に残るのは「何のために命は奪われたのか?」という苛烈な問いです 。
焼け落ちる塔も、死んでいった青年も、すべてが幻のように感じられる結末。 しかし、延子はこの詩を通じて、逆説的に ”本当に命を賭す価値のあるものとは何か” を私たちに問いかけているようにも思えます 。
戦争という巨大な虚構に翻弄され、命を失った若者への挽歌。 それは同時に、現代を生きる私たちへの警鐘でもあります。
悲劇の記憶を直視し、命の尊さと儚さを凝視すること。その問いに向き合う痛みの中にこそ、生きることの意味を再確認し、傷ついた心に新たな希望の火を灯す力が秘められているのではないでしょうか 。
長沢延子の言葉は、時代を超えて、今もなお私たちの生を問い続けています。
遺されたノート―「詩」としての遺書
延子が友人たちに託した5冊のノートには、彼女が書き溜めた詩と散文が綴られていました。それは、日記であり、遺書であり、そして何より ”作品” でした。
彼女は、自分の死を計画的に準備していました。清書された文字、整理された構成。それは、自分の言葉を後世に残そうとする、明確な意志の表れです。彼女にとって、死ぬことと書くことは、分かちがたく結びついていました。死は終わりではなく、彼女の作品を完成させる締めくくりの行為だったのです。
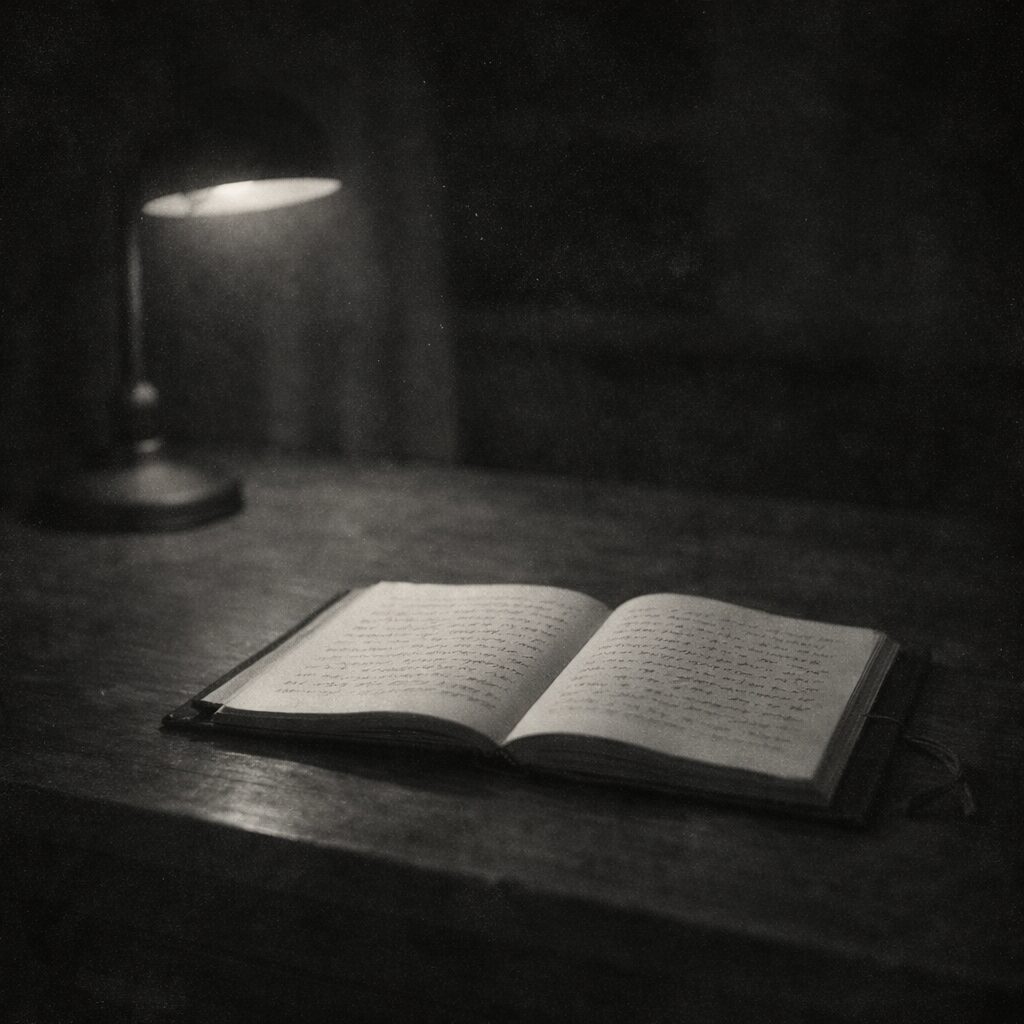
このノートは、長い間友人たちの手元で眠っていました。しかし、彼女の死から16年が経過した1965年、ついに『海 長澤延子遺稿集』として出版されます。友人たちの献身的な尽力によって、延子は死後、初めて詩人として世に送り出されたのです。
「白い玩具」を読む――絶望への問いと再生への希求

導入――「白い玩具」への問い
1948年(昭和23年)5月。 16歳になった長沢延子が綴った長編詩「白い玩具」。
全11連・66行からなるこの詩のタイトル脇には、萩原朔太郎の一節「祈るが如く光らしめ」が引用されており、深い絶望の中にも、祈りにも似た光への希求が示唆されています。
戦後の混乱期にあって、延子はこの詩にどのような再生への願いを託したのでしょうか。 今回は、彼女の思想的転換点とも言えるこの作品を読み解きながら、 ”純粋な魂は、汚れきった現実の中でどう生きるべきか” という問いについて考えていきます。
白い玩具 ――祈るが如く光らしめ――朔太郎
すゝけたエレジイの上に音もなくすわり
透明な眼(マナコ)を持った 白い玩具よ
――答えてはくれまいか
今宵歩み疲れた私の背中は
読み散したページの堆積にゆがみ
あざけりつゞけた唇は紫にあせて
馬鹿馬鹿しい幻に追いかけられ通しの胸ながら
未だにさめぬこの悶えが
心ゾウと肺ゾウの血管をふるわす
書きあきたペンには
古くさいインキの匂いがしみつき
石のように固ったペンダコが
ナイフでけずっても落ちぬ青と赤に染められ
瞳には血脈が浮き
机は書きためた原稿の重さに堪えられず
生命の辞書には
アンダーラインが埋めつくされた
さて今宵答えてはくれまいか
私の心は黒ずんだ倦怠にしおれ
深いまつげが絶え間なくふるえる
黄ばんだ掌にさびついた時計をにぎり
白い玩具よ
答えてはくれまいか
たしかにお前はいちぶしじゅう知っている
書斎の塵埃にもまれて
インキ壺のうめきさえ
開けてはいけない
人間の顔が見える
あの窓とカーテンは開けてはいけない
床のよどみ切った砂ぼこりをなめまわし
シャツの胸をはだけ
もう何も見えないのだ
お前だけが
めずらしい白さで極だっている
やぶり捨てた三冊のノートよ
あれには何が書いてあったか
何時か咲いていた紅い花のことか
均衡を失った天井が間近に破れおち
汚れにふるえながら
まだ足らないのだ
私はモルヒネ患者なのか
切れかゝった毒素
うつろな肉体をきしませて
ふくれあがる中枢神経の怒号
白い玩具よ
――答えてはくれまいか
今宵臨終の眼をお前に投げかけ
汚濁に沈み行く哀願の魂に
さびたセコンドを押しのけ
転身は私に汚濁を示した
この世のあらゆる汚濁
この地球をつきぬけて
どこかの星群のそれをも呑みこみ
あゝもっと汚せ
何のためらいも後くされも残さず
全ての因縁を最後の力でけっとばし
――今は行くだけだ
煤煙にまみれた原色の人間性
大工場に押しつけられた貧民街へと
断末魔にふるえる魂を
軽やかに抱きとり
この窓を捨てこの塵埃を捨て
新たな汚濁へとお前は去るのだ
白い玩具は祈るがごとく
我が後方に光り光り
出典元:友よ私が死んだからとて : 長沢延子遺稿集
[出帆新社]
(国立国会図書館デジタルコレクション)
沈黙する純白――玩具=幼心/純粋性の象徴

物語は、静かな部屋の片隅から始まります。
古びた哀歌のレコード盤の上に佇む、一つの「白い玩具」。 透明な眼を持つ西洋人形のようなその姿は、かつての純粋さや、傷つきやすい幼心の象徴のようにも見えます。詩の語り手は、その玩具に向かって静かに問いかけます。
すゝたエレジイの上に音もなくすわり
透明な眼を持った
白い玩具よ
――答えてはくれまいか
しかし、玩具は沈黙を守り続けます。語り手はその沈黙に、自身の行き場のない苦悩への答えを求めようとするのです。
「転身」の決意:潔癖さを捨て、汚濁の現実へ

詩の中盤、語り手の言葉は激しさを増し、ある重大な決意が語られ始めます。 それは「転身」――すなわち、自らの生き方を根本から変えるという宣言です。
この世のあらゆる汚濁
この地球をつきぬけて
どこかの星群のそれをも呑みこみ
あゝもっと汚せ
詩中で叫ばれるこの言葉は、衝撃的です。 ここで描かれる「汚濁」とは、戦後の混乱した社会や、人間の持つ逃れられない罪深さを指しています。 かつての延子であれば、それを潔癖に拒絶したかもしれません。しかし、16歳の彼女は違いました。理想の純粋さに閉じこもるのではなく、あらゆる因縁を蹴飛ばし、自ら進んで現実の泥濘(ぬかるみ)へ飛び込もうとするのです。
この背景には、親友へ宛てた手紙に記された、彼女の強い意志が投影されています。
「私は生への純潔を求めて全てのあいまいな態度を唾棄して唯物論に転身します。(中略)生きている私はとびこんで行くのです」
友よ私が死んだからとて : 長沢延子遺稿集(出帆新社 p145)より
死へと逃避した詩人・原口統三とは対照的に、延子は「生への転身」を選びました。 生きることは、汚れること。そのすべてを受け入れてでも生き抜こうとする、痛切な覚悟がここにあります。
絶望と隣り合わせの希望

終盤、白い玩具は語り手の目前から去っていきます。 「この窓を捨てこの塵埃を捨て/新たな汚濁へとお前は去るのだ」と詩は締めくくられ、純粋な心(白い玩具)は、部屋を出て貧民街の現実へと旅立っていくのです。
玩具は最後まで一言も発しません。 この結末について、批評家の福島泰樹氏は、まるで萩原朔太郎『絶望の逃走』ではないか、と述べています(皓星社・Webコラム「 メルマガバックナンバー 」)。
玩具が去った後に残るのは、明るい未来ではなく「暗い死の荒原をゆく馬車」が残した轍(わだち)である――。 つまり、この時期の延子にとって「希望」とは、常に「絶望」と隣り合わせのものであり、再生への希求もまた、深い傷を引きずりながら進む過酷な道のりだったのです。
結び:沈黙の中に「再生」の答えを探して
「白い玩具」を読み終えたとき、私たちの胸には一つの問いが残ります。
純粋な魂は、無辺の汚濁の中でどう再生し得るのか?
答えを求めて語りかけた白い人形は、沈黙のまま旅立ちました。 それはまるで、延子自身が生きる意味を求めて、泥だらけの荒野へ歩み出した姿のようにも思えます。
美しい詩を創造し、それを鑑賞する行為そのものが、生きる力を取り戻すきっかけになり得るのだとしたら。 この詩の沈黙は、読む私たち一人ひとりに、それぞれの答えを見出す余地を与えてくれているのかもしれません。
絶望の淵で紡がれた、祈りのような言葉。 それが今、私たちの心に小さな光を灯し、”それでも、汚れても、生きていこう” とする力をそっと呼び覚ましてくれるのです。
「墓標」を読む――家への呪詛と闘争の詩学

墓標
うしなわれた数々の幼ない画集の中
流れながら野辺おくりの郷愁の唄が光る
朝飯にと供せられた一切れのパンに
あのキューバの砂糖をつけて口に運べば
あまりに困惑した眉根がうかぶ
――自ら訪れて年をとろうとした
苔むした墓場のかぎ
――自ら生命をたとうとした
あまりに底抜けな空の青さよ
死にそこなった疲れに
むなしく窓外をみつめた時
あてどなく雪は降りつもっていた
そのゆくては見えず
充血した脳髄をひやすように
どこともなく駈けて行く
馬車のわだちを聞いたのだ
小さな風気孔から血が降ってくる
誰が誰のために流した血なのかと
この別れに何と名をつけろと迫るのだ
私はドアを閉めて外へ出た
閉ざされた窓に風が吹きつける
雪よ あの家を埋めろ
私の墓標はこの涯ない草原に群をなす
裸体の人々の中にある
すでに家を捨てた者が
逞しく この草原を闘いの色に染めあげている
私は一本のわかい葦だ
傷つくかわりに闘いを知ったのだ
打ちのめされるかわりに打ちのめすことを知ったのだ
雪よ 闘いの最中にこの身に吹きつけようとも
もうすでにおそい
私は限りない闘いの中に
私の墓標をみた
出典元:友よ私が死んだからとて : 長沢延子遺稿集
[出帆新社]
(国立国会図書館デジタルコレクション)
冒頭一行の衝撃――〈雪よ あの家を埋めろ〉
延子の代表作の一つ、「墓標」は、彼女の精神世界を理解する上で、最も重要な作品です。
雪よ あの家を埋めろ
私の墓標はこの涯ない草原に群をなす
裸体の人々の中にある
すでに家を捨てた者が
逞しく この草原を闘いの色に染めあげている
この詩の冒頭、「雪よ あの家を埋めろ」という一行は、強烈な呪詛です。雪は、すべてを覆い尽くし、埋葬する力を持つ自然の暴力。彼女は、自分を苦しめた ”家” が、雪によって跡形もなく消え去ることを願っています。
ここで言う「家」とは、もちろん物理的な建物だけを指すのではありません。それは、家族制度、伝統、因習、女性に課せられた役割、そして戦後もなお残存していた封建的な価値観の象徴です。延子にとって、それらはすべて埋葬されるべきものでした。
注目すべきは、彼女が、すでに家を捨てた者たちと連帯しようとしている点です。彼女は孤独ではない。いや、少なくとも彼女は孤独でありたくなかった。「草原」という開かれた空間で、裸体の人々(あらゆる装飾や社会的役割を剥ぎ取られた、純粋な個人)と共に、「闘い」の色を染め上げる。それが理想でした。
厭世ではなく、闘争――能動的な怒りの言葉

「墓標」を読む際に注意すべきは、これが単なる厭世詩ではないという点です。彼女は世界に絶望して、受動的に死を選んだのではありません。その言葉は極めて能動的で、攻撃的です。
同じ詩の次の連で、こう宣言しています。
傷つくかわりに闘いを知ったのだ
打ちのめされるかわりに打ちのめすことを知ったのだ
ここには被害者としての自己憐憫はありません。傷つけられる側から、傷つける側へと移行することを宣言しています。道徳的に正しいか否かとは別の次元の、一つの生きざまの選択でした。
彼女は社会や家族に対して「NO」を突きつけましたが、ありきたりな拒絶ではなく、新しい世界(家のない草原、裸体の連帯)を創出しようとする意志を含んでいました。
その新しい世界は、彼女の死によって、実現することはありませんでした。しかし、その未完の意志は、図らずも後の世代に受け継がれていくことになります。
「別離」を読む――死と再生のエレジー

長沢延子が残した数ある詩稿の中でも、特に強く胸を打つ作品があります。 それが、「別離」です。
これは、死を予感した17歳の彼女が、親しい友人に宛てて書いた遺言のような趣きを持つ作品です。 死の直前、自身の死後について友に語りかけるこの詩には、若くして世を去ろうとする彼女の、あまりにも切実で、そして透き通るような思いが凝縮されています。
別離
“別離の時とはまことにある・・・朝が来たら 友よ
君等は僕の名を忘れて立ち去るだろう” 原口統三
友よ
私が死んだからとて墓参りなんかに来ないでくれ
花を供えたり涙を流したりして
私の深い眠りを動揺させないでくれ
私の墓は何の係累もない丘の上に立て
せめて空気だけは清浄にしておいてもらいたいのだ
旅人の訪れもまばらな
高い山の上に―
私の墓はひとつ立ち
名も知らない高山花に包まれ
ふれることもない深雪におゝわれる
たゞ冬になったときだけ眼をさまそう
ちぎれそうに吹きすさぶ
風の平手打に誘われて
めざめた魂が高原を走りまわるのだ
友よ
私が死んだからとて
悲しんだり哀れんだりすることは無用なのだ
私にひとかけらの友情らしいものでも
抱いてくれるのなら
それはたゞ私を忘れて立ち去ることだ
世の中に別れを告げた私が
生きる人々の内に
なお映像としてとヾまることは堪えられない
私の墓を
幾度び幾たび過ぎる春秋の中で
人々の歩みを
やがては
忘られた勝鬨さえ聞くことが出来るだろう
友よ
その時こそ私の魂は歓喜に満ち
その時こそ私が死ぬ時なのだ
墓の中の魂は春にめざめ
再びの別れを
その墓に告げる時なのだ
友よ その時こそ忘却の中で
大きな旗を
大空に向って打ちふってくれ
その逞ましい腕のつづく限り
私に向って打ちふってくれ
友よ
別離の時とはまことにある
朝が来たら――
君等は私の名を忘れて立ち去るだろう
出典元:友よ私が死んだからとて : 長沢延子遺稿集
[出帆新社]
(国立国会図書館デジタルコレクション)
誇り高き孤独と、拒絶の美学

詩は、親しい友への静かな呼びかけから始まります。
友よ
私が死んだからとて墓参りなんかに来ないでくれ
花を供えたり涙を流したりして
私の深い眠りを動揺させないでくれ
自分が死んでも、どうか墓参りなどしないでほしい――。 この言葉には、死後に自分が美化されたり、あるいは憐れまれたりすることへの明確な拒絶と、”友人たちにこれ以上悲しみや負担を背負わせたくない” という優しさが滲んでいます。
葬儀的な哀悼さえも拒むこのフレーズに表れているのは、17歳の少女の「誇り高い孤独」です。誰かに慰められることすら拒み、ただひとり静かに去ろうとするその姿勢に、私たちは胸を打たれずにはいられません。
魂が帰る場所―雪と静寂の聖域

延子はさらに、自らの墓を、「何の係累も無い丘の上」に、名も知らぬ高山植物に囲まれて建ててほしいと願います。
生前、家庭や世間の因習に縛られ、傷ついてきた延子。 彼女にとって、人里離れた高地で誰の記憶にも煩わされず眠ることは、家や社会といったしがらみから解き放たれる究極の自由を象徴していたのでしょう。
雪に閉ざされる静寂の中でのみ、魂が「眼をさます」と語るくだりには、真っ白な冬のイメージとともに、美しさと寂しさが同居しています。 傷だらけの魂が最後に辿り着いた、静謐な聖域。延子は冬の眠りと大自然の孤独の中にこそ、真の安息を見出そうとしていたのです。
「私を忘れてくれ」―逆説的な愛と再生

一見すると虚無的にも思えるこの詩ですが、読み進めると不思議な能動性と未来へのまなざしが潜んでいることに気づかされます。
延子は友に向かい、こう告げます。「私にひとかけらの友情らしいものでも抱いてくれるのなら/それはたヾ私を忘れて立ち去ることだ」
生きる人々の記憶の中に、自分が映像として留まり続けることは耐えられない――。 ここには、死後ですら他者の記憶に縛り付けられることへの抵抗があります。
延子にとって本当の「別離の時」とは、愛する友人たちが自分の名を忘れ、それぞれの日常へ旅立っていく朝のことなのでしょう。その瞬間こそ、自分も重荷から解放され、友人もまた自由になれる。 「忘れてほしい」という願いは、裏を返せば「残された者は、過去に囚われず前を向いて生きてほしい」という、延子なりの静かな優しさとエールなのです。
悲しみの旗ではなく、未来への旗を

詩の終盤、延子は非常に印象的で、意外なイメージを描き出します。
友よ その時こそ忘却の中で
大きな旗を
大空に向かって打ちふってくれ
自分という存在が忘れ去られた暁には、大空に向けて大きな旗を振ってほしい。 ここで突如現れる「旗」は、延子の詩に通底する ”闘い” の象徴です。
かつて彼女は、代表作「墓標」において〈雪よ あの家を埋めろ〉と叫び、古い権威の埋葬を願いました。しかし、この「別離」では真逆に、大空へ掲げる旗に新たな門出を託しています。 友人たちが自分を忘れ、それでもなお力強く未来へと進んでいくことへの祝福。振られる旗は、悲しみの合図ではなく、再生の象徴としてひるがえっているのです。
結び:「喪失」から始まる再生の物語
評論家の福島泰樹氏は、延子の硬質でしなやかな言葉の中に「詩人長澤延子の生への決意がこめられている」と指摘しています。
延子は決して世界への関心を失ったわけでも、未来に絶望しきっていたわけでもありませんでした。 むしろ、自らは姿を消しつつも、戦後の荒地を切り開き歩んでいく人々の未来を、万感の思いで見守ろうとしていたのです。自分が完全に忘れ去られたとき、それは自分が歴史の一部となり、未来への一体感を得られた証なのだ、と。
この詩は、一人の少女の絶望の告白であると同時に、後に続く私たちへ遺された ”贈り物” です。
私たちは大切な誰かを失ったとき、どうすべきなのか。 延子は「泣かないで」「忘れて」と語りかけます。それは、悲しみの中に留まるのではなく、新しい朝に向かって歩き出しなさいという、優しい背中押しなのかもしれません。
どんな悲しみもいつかは日常に溶け、生者は再び歩き出せる。それこそが、人生の再生なのです。 「別離」という詩は、時代を超えて今もなお、喪失の痛みを抱える私たちの心に、静謐な温もりと「悲しみを超えてしか宿せぬ生き切る力」を灯し続けています。
1960年代という再発見――全共闘とバリケードの中で

詩が壁に貼られたという出来事(象徴性)
延子の詩が再び光を浴びたのは、1960年代後半のことでした。1968年から69年にかけて、日本中の大学で学生運動が高揚します。学生たちは、大学の権威主義、日米安保条約、そして資本主義社会そのものに対して異議を唱え、バリケードを築き、機動隊と衝突しました。
1969年1月、東大安田講堂の攻防戦。機動隊の放水と催涙ガスの中、立てこもる学生たち。その中の何人かは、長沢延子の詩を書き写し、壁に貼り付けていたと言われています。
なぜ、延子の詩は彼らに届いたのでしょうか。
「家への反逆」→「国家/大学への反逆」への共鳴
それは、延子の ”家への反逆” が、彼らの ”国家や大学という巨大な権威への反逆” と共鳴したからです。延子が「家を埋めろ」と叫んだように、彼らは「大学を解体しろ」「国家を否定しろ」と叫びました。
そして何より、延子の言葉には、理論や政治的な正しさを超えた、やり場のない怒りの純粋さがありました。学生たちもまた、理路整然とした革命理論だけでは説明できない、もっと根源的な生きづらさや、この世界への違和感を抱えていました。延子の詩は、そうした言語化できない感情に、形を与えてくれたのです。
こうして、1949年に死んだ17歳の少女は、1969年のバリケードの中で、再び「生きた」のです。
無名が神話になるとき――発見者たちの愛
長沢延子が完全な忘却から免れたのは、奇跡に近い出来事でした。もし、彼女が詩を友人に託さなかったら。もし、その友人たちが遺稿集を出版しなかったら。もし、1960年代の学生たちが彼女を発見しなかったら。

彼女の言葉は、紙屑として消えていたでしょう。
無名の夭折詩人が歴史に名を残すためには、必ず発見者が必要です。友人、編集者、研究者、あるいは偶然手に取った読者。彼らが、その言葉の価値を信じ、語り継ぐことで、詩人は第二の死から救われます。
延子の場合、最初の発見者は彼女の友人たちでした。彼女たちは、延子の言葉を16年間大切に保管し、出版にこぎつけました。そして、第二の発見者は全共闘世代の学生たちでした。彼らは、延子を自分たちの先駆者として、神話化しました。
こうして、無名の少女は伝説になったのです。
現代への問い――承認なき表現の純粋さ

では、長沢延子は、現代の私たちに何を問いかけるのでしょうか。
「いいね」のない時代に、書かずにいられなかった
彼女は、誰にも読まれないかもしれないノートに詩を書きました。「いいね」も「リツイート」もない時代。彼女の言葉は、数値化された承認とは無縁のところで生まれました。
現代の私たちは、投稿する前に「これはバズるか」を計算します。しかし、延子にとって、書くことは生存戦略ではなく、存在証明でした。彼女は、誰かに認められるために書いたのではなく、書かなければ自分が消えてしまう、という切迫感から書いたのです。
その純粋さは、承認欲求に疲れた現代人にとって、一つの解放を示唆しているかもしれません。誰かに読まれなくても、拡散されなくても、魂を込めて言葉を書くことには意味がある。いや、むしろ浮ついた視線には捉えられないからこそ、言葉は清洌になり得えているのだと。
拡がらぬ長沢延子の言葉に触れるには
長沢延子の遺稿集『海 長澤延子遺稿集』(1965年刊)は、現在では古書としてしか入手できません。また、群馬県立土屋文明記念文学館では、定期的に「夭折の詩人展」が開催され、彼女の遺品や詩稿が展示されることがあります。
彼女の言葉に触れたいと思った方は、まずは図書館で探してみてください。あるいは、インターネット上にも、彼女の詩の一部が引用されている評論や記事があります。筆者は、国立国会図書館デジタルコレクションに、大変お世話になりました。
無名であることは、アクセスの困難さを意味します。しかし、その困難さゆえに、彼女の言葉に辿り着いた時の感動は、より深いものになるでしょう。
次回予告:黄金の鳥籠から鉄路へ
次回は、長沢延子と同じく自死を選びながら、対照的な環境で育った詩人を取り上げます。
久坂葉子――川崎財閥の血を引く名家の令嬢。神戸の山手に育ち、何不自由ない生活を送っているように見えた彼女は、なぜ21歳で阪急電車に身を投げたのか。
「肩書きもいらず勲章もなく」と歌った彼女の詩と、芥川賞候補となった小説「ドミノのお告げ」。そして、「幾度目かの最期」という遺稿のタイトルが意味するもの。
貧困の桐生と富裕の神戸。地方と都会。しかし、二人の少女を死へと追いやったものは、驚くほど似ていました。
次回、久坂葉子の「黄金の鳥籠」を開きます。
どうぞお楽しみに。
(第2回 完)



コメント